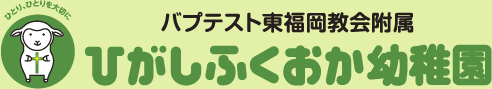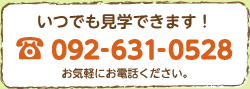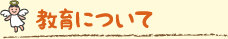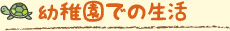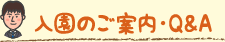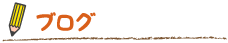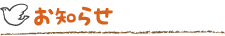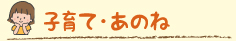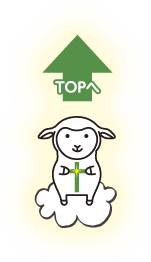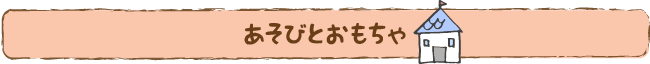
過去ログ
お友だちと一緒に
おもちゃインストラクターのMです⭐
ひがしふくおか幼稚園には、たくさんのおもちゃがありますが、その中でもほし組の子どもたちは、「バランスタワー(アントン・シーマー社)」で遊ぶことが大好きです👦👧
ルールは簡単で、順番にサイコロで出た色のブロックを抜き、上に積み上げていき、タワーを倒した人が負けという、ジェンガに似た遊びです。ブロックを抜くときの力加減や、倒れないようにバランス等を考えながら行うため、大人の私も集中して、子どもたちと一緒に遊んでしまいます😂
面白いことに、遊び始めた頃と現在では、ブロックの取り方が変化しています。遊び始めた頃は、真ん中のブロックを取る子がほとんどだったのですが、端のブロックから取る方が面白いんじゃないか?という声から、現在は端のブロックから取る子が増えました。
また、お友だちに協力する声掛けが多いのも素敵だと感じる、子どもたちの姿です💙大人の私が友達とバランスタワーをすると、「これを取ったら(倒れるから)いいんじゃない?」と、きっと相手が不利になる言葉を掛けると思います。しかし、子どもたちは、「このブロックは簡単に取れそうだよ!」、「今バランスタワーしてるから、周りのお友だちは静かに歩いてね!」等、お友だちと協力して遊ぼうとする言葉掛けが、とても多いです💞勝ち負けはありますが、敵ではなく、一緒に遊ぶお友だちと認識しているのだと思います☺遊びの中で、集中力や指先の力加減だけでなく、お友だちと協力すること、コミュニケーション等も学んでいるのだなあと感じます🌱
ドミノ倒しのように並べて遊んだり、積み木のように構成遊びを楽しんだり…と、多様な遊び方で遊べるのも、子どもたちがバランスタワーが好きな魅力の一つなのかもしれません。
遊びの中に、子どもたちの学びはたくさん詰まっています。たくさん遊んで、たくさん学んで、大きく成長する姿を、これからも見守っていきたいと思います😊✨
ぬいぐるみの魅力
幼稚園のお人形たちがだいぶ古くなったので数年前からちょっとずつですが、
保護者会からのクリスマスプレゼント🎄でいただいたり、買い足したりしてきました🐻
新しいおにんぎょうに、子ども達は「わぁっ😆✨✨」と喜び
すぐにぎゅっと抱きしめて、甲斐甲斐しくお世話をしていました。
古いお人形はもう寿命かなぁ・・・😢と、
ちょっぴり胸を痛めつつ子ども達の姿をよく見ていると
実は、古いお人形の中にお気に入りがいる子もいて、
自由遊びの時間に、必ず自分の“大切な一体”を持ってきて愛してくれています🐭💓
先日、卒園生のA君👦のお母さんとぬいぐるみの話になり(ぬいぐるみが大好きな子でした)
「小学生になった今も、抱きしめて寝ていますよ。」とおっしゃられて、ほほえましく思いました。
またある時は、登園時に車の中で大切そうににぎりしめていたBちゃん👧が
「生まれた時からのお気に入りです。」と話してくれたりもしました。
家の娘も、たくさんある中で、特別に気に入っているぬいぐるみがあります。
ドイツ生まれ🇩🇪のテディベア🐻で抱き心地もよく、寝る時もお風呂も(たまに😅)一緒です。
子ども達が愛情をこめて、ぬいぐるみのお世話をしてくれる姿を見ると、
ぬいぐるみは、子ども達の心に寄り添って癒しを与えてくれたり安心させてくれると同時に
想像力をも刺激し、様々なごっこ遊びを展開させてくれる存在でもあることを実感します。
そして、子ども達の心の育ちを、支えてくれているんだなぁ。としみじみと思います🍀💭
みなさんもお気に入りの一体はありますか?
ともに
おもちゃインストラクターのEです🍀
💜東福岡幼稚園はキリスト教保育を行っている幼稚園です。キリスト保育連盟が編纂したキリスト教保育指針を保育の基盤としています。そのキリスト教保育指針に、「遊び…共に育つ経験」であり、「遊びは自由で、自発的なものであり、遊ぶこと自体が目的であって、あらかじめ目的や成果が設定されているものではない。自分らしく遊ぶことをたっぷりと保障したい。」とあるように、キリスト教保育では「遊び」を大切にしています。
また、文部科学省が定めた幼稚園教育の基準である幼稚園教育要領というのがあります。
その幼稚園教育要領では、遊びから「知識及び技能の基礎」「思考力・判断力・表現力等の基礎」「学びに向かう人間性等」が育まれ、生涯に渡る生きる力の基礎を培っていく、とあります。
このように、「遊び」とは人間の発達にとって欠かせないものであり、大切なものであることがわかります。
これらのことを学び、キリスト教保育の幼稚園で幼稚園教育を担う者として、子どもの自発性を大切にした保育をすることを心にとめて日々保育をしています。
🧡私は前年度に年長ひかり組の担任をして、今年度は満3歳そら組・年少つき組の担任をしています。その中で、子ども達の遊びの中で「おもちゃ」に関して、気付いたことがあります。
年長ひかり組の子ども達は、最初から友達や保育者と「ともに」おもちゃで遊ぶ中で、遊びをつくりあげていきます。友達の遊びに「いれて」と言ったり、友達に「○○(おもちゃ)で遊ぼう。」と誘ったりと、自分から動いて周りの人と一緒におもちゃで遊ぶことが多くあります。それは今までの幼稚園生活の中で、子ども達自身が遊びたいと思ったおもちゃがあり、そのおもちゃを通して子ども達が友達と一緒に遊ぶ楽しさを感じてきたからだと思います。最初から友達との大きな円があるイメージです。
一方、満3歳そら組・年少つき組は、おもちゃで遊ぶ時に、最初は個々で遊んだり、保育者と遊んだりします。そのうちに友達がしていることが気になり、「いーれーて」と言って入り、そこから段々と友達と「ともに」遊ぶ輪が広がっていきます。徐々に友達との円が大きくなっていくイメージです。
このようにその年齢なりの在り方で、おもちゃを通して周りの人と「ともに」関係を築いていき、その積み重ねの中で子ども達は育っていきます。
❤私が各年度のキリスト教保育を行う上でいつも意識しているものとして、キリスト教保育連盟のその年の年主題があります。
2025年度のキリスト教保育連盟の年主題は「ともに」です。私は、この「ともに」は遊びを通しても実現されるものだと思います。子ども達は周りの人と「ともに」過ごしたり、友達と「ともに」遊んだりする中で、たくさんのことを経験します。その中で様々なことを学び、愛情を感じ、そこから自分や周りの人たちのことを大切にしていくことができます。
これからも子ども達が遊びとおもちゃを通して、「ともに」育っていくことができたらと思います✨🌙
第16回おもちゃの広場
7月26日【土】に、幼稚園で第16回目の「おもちゃの広場」を開催しました。
幼稚園でこんなに長く継続して「おもちゃの広場」を開催しているところは珍しいそうです🙂
今年も暑い中、園児のみではなく、地域のたくさんのお子さんと保護者の皆様がご参加くださり、大変うれしく思いました😊
夏休みになって久しぶりに会った年少組女児二人が、楽しそうにおままごとをしている様子を、保護者の方々が笑顔でご覧になられたり、初めて会った小さい子ども同士が一つのおもちゃで遊ぶ姿を保護者の方々があたたかく見守ってくださったり、卒園児が『クーゲルバーン』でビー玉が上手く転がるように一生懸命組み立てていたり、それぞれが、幼稚園のおもちゃで楽しそうに遊ぶ姿を拝見することができました。
午前の「ゲームで遊ぼう」には、親子で参加して、楽しんでいただきました。
「ステッキー」というゲームは、木のリングに赤と青と黄色の細長い棒を入れて机の上にたてたものから倒さないようにサイコロの色と同じ棒をにぬいて、倒した人が負けという簡単なルールのゲームですが、子どもではなく、なんと大人が3回も倒してしまいました
また「マイファースト果樹園」は、果物とカラスの絵が描かれているサイコロを参加者が順番に振って果物の絵が出たら同じ絵の木製の果物をを箱の中に入れていき、カラスが出たらカラスの道を進み、カラスの道が終わるよりも早く果物を全部箱の中に入れたら良いという協力型のルールのゲームです。なぜかサイコロのカラスが全く出ることがなく、すべての果物の収穫を終えることができました。
最後の「ハリガリ」というゲームは、参加者が同時に自分の持っている果物の絵カードを出し、同じ果物が5個になっていたら、ベルを鳴らし、一番早かった人が果物カードをもらうというルールですが、このゲームもなんと大人ではなく幼稚園児が勝ちました。
「作って遊ぼう」の「お魚釣り」では、魚に油性ペンで🖊でお絵かきをして、保護者も子どもも楽しむ姿が見られました。
午後の「げーむであそぼう」は、参加者が多く、3グループに分かれてしましたが、特に「バランスタワー」は大盛り上がりでした。大人も子どもも年齢に関係なく遊べるおもちゃは、本当に楽しいものですね❣
「つくってあそぼう」では、「回転寿司」という保育者考案のおもちゃを作りました。中には、見本を見ただけで、どんどん作る幼稚園児や自分なりに工夫して作る小学生もいました。子どもたちの想像力に驚かされました🤩
参加してくださった方々が、笑顔になったり、楽しかったと思って下さっていたら、私たちも心から嬉しく思います。
ご参加下さり、本当にありがとうございました😊
子どもの学びを支えるおもちゃの力
おもちゃインストラクターのAです。2回のコラムで話題となった「遊び=学び」の具体例をひとつご紹介いたします😌
年長のAくんは、積み木や組み立てクーゲルバーンなど、自分の思い描く形を、おもちゃを使って表すことが大好きです。思い通りにいかないことに葛藤しながらも、時間をかけて少しずつ完成へと進めていく力があります。
ある日のお部屋遊びの時間、AくんはBくんと一緒に、「Piks(OPPI社)」というおもちゃで遊び始めました。これは、3種類の高さのシリコン製三角コーンと木製プレートを、崩れないように積み重ねていく、シンプルながらも奥深い遊びです🍀
Aくんは今までに何度か遊んだ経験があり、「もうできない」と諦めたり、「やっぱりやってみる」と挑戦したりを繰り返す中で、少なくとも3つのコーンがあれば、プレートを支えられることを、自らの体験を通して学んできました。
その日は、大きな机の上に広げたパーツと「ゲットスマートカード」を見ながら、どれを作ろうかとBくんと一緒に相談していました。いくつか作っていくうちに、「次はこれにしようかな」と、どんどん難しいものに挑戦していきます。しかし、難しくなればなるほど、崩れやすくなり、作り方に対して意見の食い違いが出てきました。2人でどのようにしたらいいか考え、指示係と作成係に分かれて作ることにしました。
やがてBくんは満足して別の遊びにうつりましたが、Aくんは一人でコツコツと取り組み続けました。最も難易度が高いカードは非常に難しく、何度も崩れてしまいます。BくんもAくんの様子を見に来ては、気にかけている様子でした。また、Aくんの「なぜかできないんだよなあ」と呟きを聞いたCちゃんが「やってあげようか」と手伝うこともありました。
そのような過程をふみ、担任が見守るなか、Aくんは真剣な表情で何度も挑戦し、ついに完成させました✨
その喜びは本人だけにとどまらず、BくんやCちゃん、そして周囲で遊んでいたクラスの友達にも広がり、「Aくんがこんなに高く作ったんだよ」とみんなで一緒に喜びあいました。
この遊びの中には、指先をたくさん使う、バランスをとる経験、力加減の調整、より良い作り方を探る試行錯誤、論理的思考力の育成、自分で改善点を見つけて再挑戦する問題解決力、完成したときの達成感を、共に喜ぶ嬉しさ、他者の喜びを分かち合う経験…といった、たくさんの学びがつまっています💖
「遊び=学び」とはまさにこうした体験を指します。そして今回の学びを支えたのが、「Piks」というおもちゃでした。良質なおもちゃは、遊びの幅が広げ、学びの可能性を大きく広げてくれます💫
ひがしふくおか幼稚園では、このような良質なおもちゃを集めた「おもちゃの広場」を、明日7月26日(土)に開催いたします。ぜひ、親子でたくさんのおもちゃに触れ、一緒に遊んでみてください。みなさまのお越しをお待ちしております😊💓
- 1
- 2