パズル



『パズル』には、色々な種類があり、また難易度も様々です。指先で十分に物をつまむことができる


最初から、すべてのピースをはめ込む方法は、子どもにとっても、また、途中で子どもが投げ出した時に、それを片付けなければいけない大人にとっても、











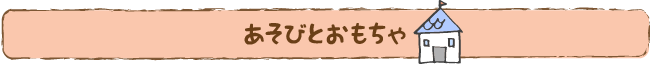



『パズル』には、色々な種類があり、また難易度も様々です。指先で十分に物をつまむことができる


最初から、すべてのピースをはめ込む方法は、子どもにとっても、また、途中で子どもが投げ出した時に、それを片付けなければいけない大人にとっても、










