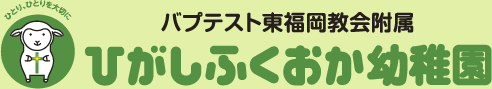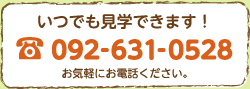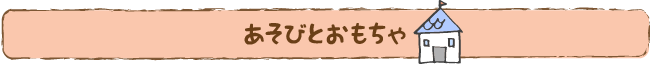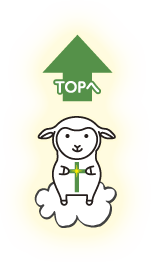過去ログ
二人で一緒に 『組み立てクーゲルバーン』



私はその様子を見ながら「そんなに難しいこと、この


ところが、





私は「エ?本当にこの
その後は、出来上がったクーゲルバーンに、ビー玉を何度も何度も繰り返し転がして遊んでいました。途中で、







手袋人形













ちなみに、

今、私はこの二つの

これって、
寒~い冬に楽しい遊びは?
【大寒】とは










寒いからと言って子どもたちがずーと部屋に閉じこもっていると、



こんな時こそ、戸外で遊びたくなる遊びをしてみませんか?
その遊びとは、一説によると平安時代に中国から日本に伝わり、江戸時代に庶民の遊びとして定着したといわれる
できれば、お子さんとご家族ご一緒に手作りでビニール凧を作っていただけたらと思います。作り方は、意外と簡単です。「ビニール凧の作り方」で検索していただくと、いろいろな作り方が出てきます。ぜひ、お試しを!!
凧を作ると、遊びたくなります。 → 遊びたくなると、子どもは寒くても外に出かけます。 → 凧を揚げるには、最初は走らなければなりません。 → 走ると少し体が温かくなります。→ 最初は






市販の


カードゲーム【NINE TILES】(ナインタイル)






と言うことで、今回は



それは【NINE TILES】(ナインタイル)というカードゲームです。ゲームのタイトどおり、9枚の小さなカードを縦横に3枚づつ並べて遊びます。でも、9枚のカードには表と裏にそれぞれいろいなマーク(模様)が描かれており、指示カードと同じ並びに正確に並べなくてはいけません。ただカードを並べるだけなのに、


今は、

でもやはり最初はどんな遊びでもゲームでも、


集団遊び 『鬼ごっこ』かな? 多分そうらしい
最近、






一人の子どもが年長組のマネをして、






その




まだまだ集団遊びの

人と