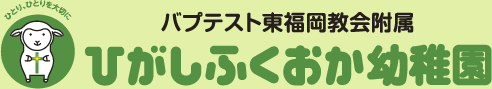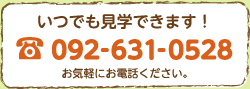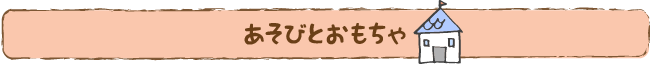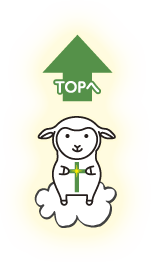過去ログ
積み木 たかーく積んだよ!!
👧🏻年長組の女の子が、一人で約200個の積み木を積み重ね、高さ約160cm積み木の塔を作りました。以前、👫年上のお友だちや同学年のお友だちが同じように作っていたので、その積み方を覚えていたようです。
👧🏻気に入ったその積み方を楽しんでいるだけの時期もありましたが、最近では「より高く!」との目標ができ、😪せっかく途中まで積んだのに、他のお友だちが近づいたり触ったりして崩れてしまい、😯最初から何度も積みなおすこともありました。
👧🏻この日も同じように😥途中で崩れることがありましたが、それでもあきらめずに、😠根気よくチャレンジしていました。全ての積み木を積み上げたいとの思いから、どんどん高くなって手が届かなくなると、椅子を持ってきてそれに乗り、そして背伸びをしてやっと全ての積み木を積み終わりました。😀とても達成感を感じたようで、😍しばらくじっと一人で積み木の塔を眺めていました。そして、👧🏻その女の子は積み木の塔と背比べをしました。一緒にいた👩私にも背比べをするように勧めてくれました。私は身長が152cmなので、積み木の塔の方が高く、👧🏻女の子は、「先生より、私の積み木が高い!」と😊大喜びでした。その後、👨園長先生をはじめ、幼稚園のすべての👩先生たちが積み木の塔と背比べをし、👧🏻女の子は「先生の方が大きかった」とか「同じくらいだった」とか言いながら、みんなからたった一人で根気よく最後まで作ったことや、自分で目標を決めてそれを実行できたことなど、💝たくさんたくさん褒めてもらいました。
👧🏻この女の子は今回の積み木だけでなく、他のこともコツコツ頑張る子どもです。これからの人生も、いろいろなことに対して、今回の積み木と同じように💖自分の目標に向かって、一生懸命に努力してほしいと🍀願っています。
さかさま『かるた』
⛪幼稚園には、20年以上前に作られた🖍手作り『かるた』があります。以前に勤務されていた👨👧👧先生方の作品だと思います。1枚の絵札の大きさは、A4用紙の半分くらいの大きさで、とてもわかりやすい絵が描かれています。読み札は、トランプくらいの大きさで、文字は、全て2文字です。例えば、「かめ」「いぬ」「あめ」などです。
預かり保育に時間に、いろいろな学年の👧🏻子どもたちが一緒に🖍その『かるた』で遊んでいた時のことです。なんだか、🙄聞きなれない言葉が聞こえてきました。「めか」「ぬい」「めあ」・・・ 🤔あれれ?と思って聞いていると、なんと全ての読み札を、逆さまに読んでいたのです。🖍手作り『かるた』で何度も遊んで、もう十分に楽しんで、それで誰かが逆さま読みを思い付き、その方法で遊んでみると😝面白かったのでしょう。
遊びには、それぞれの遊びに適したルールがあり、一緒に遊ぶ仲間がそのルールに従って遊ぶことは大切ですが、遊びながら自分たちで新たな方法やルールを生み出し、それを試したり楽しんだりすることも、とても大切だと思います。自分たちで新しいルールを作り、それを仲間と一緒に楽しんでいる子どもたちは、❣笑顔いっぱい、😆げらげら笑いながら🖍手作り『かるた』を楽しんでいました。🖍この『かるた』を作ってくださった👨👧👧先生方、今も子どもたちは🖍この『かるた』を大切に使い、🤗とっても楽しんでいますよ! 🖍『かるた』を作ってくださり、本当にありがとうございました。
「ヤッター!!! すべりだい できちゃった」
👦🏻年少組のA君が、11月初旬に初めて滑り台を滑ることができ、😊とても喜んでいました。「え?年少組なのに、できなかったの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんね。実は、東福岡幼稚園の園庭の滑り台は、ちょっと特別な滑り台なのです。ジャングルジムの一角に滑り台が設置されており、ジャングルジムを一人で登ることができなければ、滑り台を滑ることもできないのです。お友だちが楽しそうに滑り台で遊んでいるのを見て、いざジャングルジム登りに挑戦してみるのですが・・・ 見るは簡単、するは困難・・・ ジャングルジムの高さに😬怖さを感じて、なかなか滑り台までたどり着くことができずということもよくあります。いくつもの困難や課題を乗り越えて滑り台にたどり着く、それが東福岡幼稚園の滑り台なのです。ですから、初めて滑り台を滑ることができた時には、😍その経験や喜びも特別なものなのだと思います。
👦🏻A君は、毎日のようにジャングルジムにチャレンジしていたのですが、途中まで登ると「😥やっぱりこわい」とあきらめていました。しかし、ある日「🤔できるかな? せんせいみていてね」と言い、どうにかこうにか、ジャングルジムを登り、念願の滑り台を滑ることができました。(私は、下や横から彼のおしりや足を支えたり、誘導をしていました)
その後、👦🏻A君は毎日滑り台を楽しんでいます。そして今日、彼は約150cmの高さの雲梯にぶら下がり、🤩自分で手を放し、飛び降りたのです。その行動には、😲😵本当にびっくりしました。
入園当初はいろいろなことに自信を持つことができず、「できない」「して」を繰り返していた👦🏻A君。今の👦🏻A君は、あのころとは別人のようです。💞子どもの心身の成長を期待し、焦らず待つことが本当に大切なことだと改めて感じました。
これ作戦!?
👫年中組4歳児の子どもの中には🙌カードゲームの😊面白さがわかり、誰かが🙌カードゲームを始めると、今までしていた遊びを止め、自分も入れてほしいということがよくあります。
その👫子どもたちが、今、好んでしている🙌カードゲームは、【レシピ】というゲームです。この🙌カードゲームは、『レシピカード』に描かれた具材(6種類の『具材カード』)を早く集めた人が勝つゲームです。🙌カードゲーム【レシピ】には、いろいろな種類のお料理があり、🥘世界の料理だったり、🍱和食だったり、🍝洋食だったり、🍰スイーツだったり、カードのセットごとにテーマが決まっています。ゲームをしながら「へえ、🇬🇳この国の人たちは、こんなお料理食べるんだ。私はまだ食べたことがない」「このお料理には、🍅こんな具材が入っているんだ」などいろいろな発見もあり、👫子どもたちの😀😖食の好みなども知ることもできます。
そのような和気あいあいとしたとても楽しい🙌カードゲームなのですが、最近の👫子どもたちは😰・・・他の参加者がほしいと思っている具材カードを自分が持っている時に、自分には絶対に必要のないその具材カードをずっとずっとゲームの最後まで持ち続け、他の参加者を😰困らせてしまうようになりました。大人の私もその作戦に引っ掛かり、最下位になってしまうことがあります。👫子どもたちは、私の😰困った顔を見て😙ニヤッと笑います。それで、自分がどのお料理の『レシピカード』を持っているのか、他の参加者にはわからないようにカード全部を裏返して行う本来の方法に変更してきましたが、誰がどのお料理を作ろうとしているのかをいち早く推測する👫子どもも出てきて、まんまとその作戦にやられてしまうこともあります。
目に見えるのも、目には見えていないものを情報として集め、その情報をもとに自分はどのように行動するといいのか? そのようなことを👫子どもたちは、このゲームから学んだのでしょう。他人に意地悪をしたり、他人を困らせるようなことをすることは、本来は人としてするべきことではありません。しかし、このゲームの世界では、👫子どもたちの成長のために、そのような経験も必要とされます。自分が他人を困らせることだけを体験して😜得をするわけではなく、反対に、他人から同じようなことをされ、😱困った体験をすることだってあります。
👦🏻👧🏻友達や👩先生と💞一緒に楽しく遊ぶ中で、👫子どもたちは、人間関係の様々なことを自然に💘学んでいるようです。
おうちでも、ようちえんにあるおもちゃであそびたい!・・・その後のその後
前々回の『おうちでも、ようちえんにあるおもちゃであそびたい!』と前回の『おうちでも、ようちえんにあるおもちゃであそびたい!・・・その後』では、⛪幼稚園で楽しく遊んでいるおもちゃで同じように家庭でも遊びたいと👧子どもが👩保護者に伝え、👩保護者がその気持ちを受け取り、同じおもちゃを購入して💓家族で楽しく遊んだというお話をお伝えしました。実はこの話には、その後のその後があったのです。
先日、家庭で⛪幼稚園と同じおもちゃを購入してもらい、👩👩👧👧家族で遊んでいることをとてもとても嬉しそうに話していた👧子どもの👵おばあさまが、ある日、👧お孫さんを⛪園までお迎えにいらっしゃいました。「お世話になりました。さようなら」とおっしゃってお帰りになられるとき、笑顔で後ろを振り向かれ「先生、あのゲーム、すごく楽しいですね! 先生は、楽しい遊びをいろいろご存じなのですね」とおっしゃいました。数日後、👧子どもの👩保護者に👵おばあさまとのことを伺うと、👩👩👧👧家族で👵おばあさまの家を訪問するときに、そのおもちゃ(カードゲーム)を持って行ったとのこと。そして👵おばあさまも一緒に、そのカードゲームで💞楽しく遊んだとのことでした。
たった一つのカードゲームが、👧子どもと👩保護者、そして👵おばあさままでの💞3世代を繋ぐ、💘素晴らしいツールになったのです。今、多世代交流の大切さがいろいろなところで叫ばれています。血縁関係でなくても、いろいろな世代が交流し、助け合うことで、👩保護者にとって心身の負担の大きい大変な👶子育てが、少し楽になることもあるようです。
良質なおもちゃは、世代を超えて人と人とを繋ぐ💘素晴らしいツールの一つになることを、👧子どもが証明した一つの例が🐣生まれました!